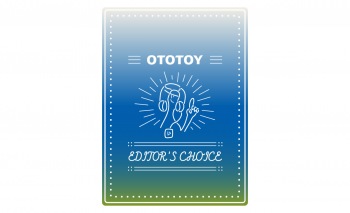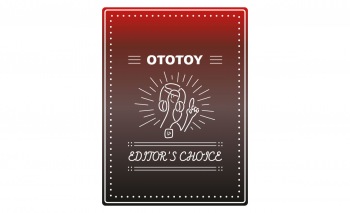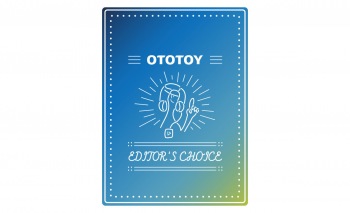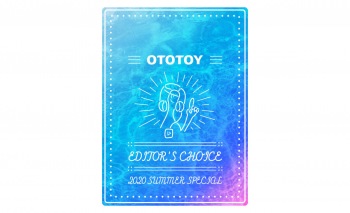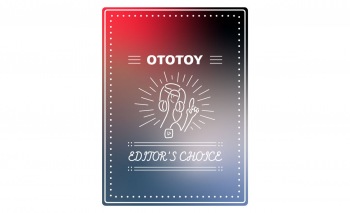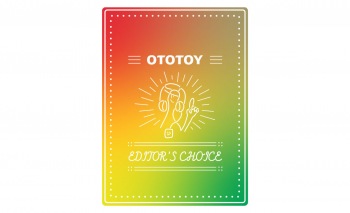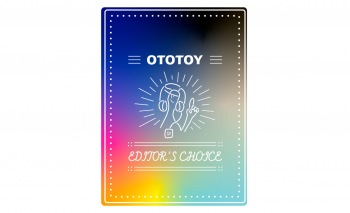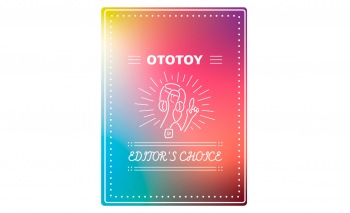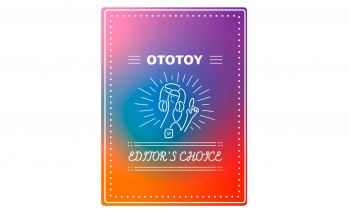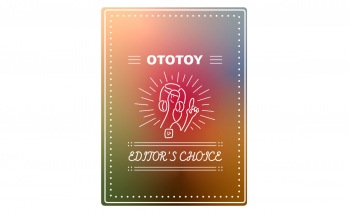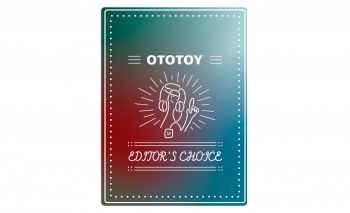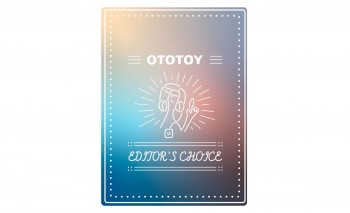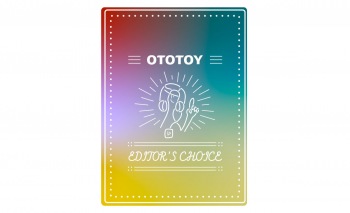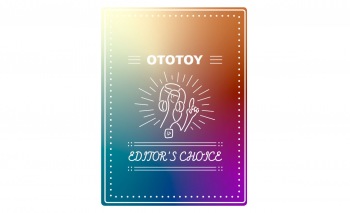OTOTOY EDITOR'S CHOICE Vol.319 テープのつなぎ目が作った音楽のフィールド──ホルガー・シューカイ
OTOTOY編集者の週替わりプレイリスト&コラム(毎週金曜日更新)
テープのつなぎ目が作った音楽のフィールド──ホルガー・シューカイ
ここ1週間ほど、若干通勤のリュックが重い。というのもA5版、450P超えのハード・カヴァーの書籍を持ち歩いているからだ。その書籍とはクラウトロックの代表的バンド、カン (CAN) の評伝『すべての門は開かれている――カンの物語』 。英の音楽誌『WIRE』の元編集長、ロブ・ヤングによる非常に詳細な取材に基づいた1冊で、さまざまな関係者への取材、そして多くの資料にあたり、当時のドイツの情況やメディアの当時の反応などなど、バンド自体とその外観も事細かに描いている。また後半にはプライマル・スクリームのボビー・ギレスピー、ポースティスヘッドのジェフ・バロウ、故マーク・E・スミス、カールステン・ニコライといった彼らに影響を受けたミュージシャン、盟友ヴィム・ヴェンダースなども登場する、イルミン・シュミットとの対談集も収録されている。
この強大な書籍、これまで知らなかったアレやコレやが満載なのだが、今日の時点で到達したのはまだ170ページほどで、ページ数にして、まだまだ3割程度といったところだ (ということは単純計算してもあと2週感前後は私の鞄は重いままだ)。全体に関してくわしくは、読了後に書評コーナー (『オトトイ読んだ』) にて書こうかと。ということでカンのプレイリス……そうOTOTOYにはカンの音源がないのだ。ならば別の話題にとも思ったのだ、バンドのベーシストであったホルガー・シューカイのソロ作の主要どころがOTOTOYには実はそろっている。
上記評伝を読んでいてひとつ驚くべきことは、初期の作品には外部のレコーディング・エンジニアがいなかったことだ。その役割を担っていたのがこのホルガー・シューカイである。彼はカン結成の直前、電子音楽の父、カールハインツ・シュトックハウゼンに師事していた。1970年代にシンセサイザーが本格的に登場する以前、電子音楽と言えばシンセ中心のものではなく、録音物としてのアナログ・テープの編集や電子的な変調などの音響的操作が中心という、ある意味でレコーディング・エンジニア的な技術で作られていたとも言える。おそらくそのあたりの経験を元に、レコーディング・エンジニアとしての素養を発揮させていったのだろう。改めて聴いてみても、たった4チャンネルでレコーディングされたというファースト、1969年の『Monster Movie』の生々しくも力強い音、まるでブレイクビーツのようなドラムの鳴りなどには驚かされるばかりだ。また彼のテープ編集技術は、カンの初期の音楽性の特異な刺激の一部となり、そしてソロ作品においても先鋭的な作品を作っていく。
1969年、カン結成当時にラルフ・ダマーズとともにシュトックハウゼンが拠点としていた、当時最新鋭の電子音楽スタジオ〈WDR〉にて、シュトックハウゼンが帰った深夜に (勝手に) レコーディングして作りあげたという『Canaxis』では、テープ・ループの重ね合わせ (つまりは実際のテープの切り貼り) で、ヨーロッパ、東アジア、中東などさまざまな音楽の要素をミニマルに折衷させて見せている。厳密な現代音楽の世界から (テープ) コラージュの方法をポップ・ミュージックのフィールドへともたらした作品とも言える (初回のジャケットは太巻きのジョイントを持つ手だ)。また演奏だけでなく、オーディオ・ファイルの編集が楽曲制作の肝となる現代のサンプリングや、もっと言えばDAW的な作曲方法の先駆けとも言えるかもしれない。彼のテープ・コラージュはカン解散後の1981年のソロ『Movies』以降もさらに磨きがかかり、次々と作品をリリースしていく。「Cool In The Pool」や「Photo Song」のようなどこかユーモラスでポップな楽曲から、ジャパンのデヴィッド・シルヴィアンとも先駆的なアンビエント作品なども。ファースト・ソロ『Moveis』収録の、エキゾチックな歌声がコラージュされた「Persian Love」は日本でもサントリー白角ウィスキーのCMにも使われ (1982年)、ジャー・ウォブルとのディスコはかのNYディスコの伝説〈パラダイス・ガラージ〉のクラシックとなり、1993年、当時勃興していたレイヴ・カルチャー以降のアンビエント・テクノに共鳴したようなアンビエント作品『Moving Pictures』などもリリースしている。ディスコ・ダブなイジャット・ボーイズ一派のアクワーバとのバイソンなるハウス・プロジェクトも晩年となる2017年にありました。ここ日本との絡みでいえばPhewのファースト・アルバムのプロデュースもコニー・プランクとも手がけている。カン以外のその後のソロ・キャリアにしても、エレクトロニック・ミュージックの分野=アンビエント・テクノやエレクトロニカに多大な影響を及ぼしたアーティストとも言える (2017年没)。